�scountry house�t�@ ���@�T�C�Y�ρ@2010�@�@�V�h��ȉ�L
�u���v����Ă��o���S�̎���

�i��O�j�s���t�@���A�S�A�h���@h205×w320×d95cm�@1998
�i���j�s�V�S�V�t�@���A�S�A�h���@h255×w76×d130cm�@1998�@�@
�M�������[�Ȃ�

�i���j�s�|�L���̒�|�@��t�@���@h50×w50×d50cm�@1999�@
�i�����j�s�|�L���̒�|�@�j�ꂽ��t�@���@h50×w50×d50cm�@1999
�i���j�s�|�L���̒�|�@�b�t�@���@h120×w45×d55cm�@1999�@�@
�K�����A���Z��
|
����
���˂ł����A�܂��͑f�ނɂ��Ă������������Ǝv���܂��B
�u�����Y�̍�i���Ǝv���Ă��܂������A���͈Ⴄ�̂ł��ˁB
�[��
�͂��A�Ă����ł��B�f�ޓI�ɂ́u���v�ł��B
����
�u���v�Ƃ́A���|�́u���v�ł��傤���B
�[��
�����ł��B
�����悤�ȑf�ނ��g���Ă��钤���Ƃł��l�̂悤�Ɂu���v�Ƃ������t��I��Ŏg���Ă����Ƃ��������A�u�e���R�b�^�v�Ƃ������t��I��Ŏg���Ă����Ƃ�������܂��B
�e���R�b�^�Ƃ����̂̓C�^���A��Łu�y���Ă��v�Ƃ����Ӗ����Ǝv���܂��Bterra�i�e���j���u��n�v�Acotta�i�R�b�^�j���u�Ă��v�B
���́u�e���R�b�^�v�Ƃ������t��I�ԍ�Ƃ������Ƃɂ͑����̂ł����A�l�̏ꍇ�͑f�ޓI�ɂ��܂�C�^���A�̃e���R�b�^�̉e���Ŏn�߂Ă��Ȃ��̂ŁA�u���v�Ƃ������t��f�ނƂ��Ďg���Ă��܂��B
����
�����f�ނł��ǂ̌��t���g���Ă��邩�ɂ���āA���̐l�̐���̃��[�c��������̂ł��ˁB�ʔ����ł��I
�[��
�l�́A���������łȂ����|���D���ŁA���|�j��Ă����̋Z�@��Ɗw�ł��������Ă��܂����B
���{�̏Ă����̒��Œ����I�Ȃ��̂Ƃ����ƁA�Ⴆ�Γꕶ�y���y��������ł����A���ւ��B���Ƃ͂���Ɏ��オ������ƍ����A�S���Ȃ�……�����Ă��܂�����ˁB
��������ɐ��m����u���p�v�Ƃ������̂����߂ē����Ă���܂ł́A�����������F�������{�ɂȂ������Ǝv����ł��B���̂��߂ɂ���܂ł̓��{�̒����I�Ȃ��̂́A�����Ȃǂ��܂ߍH�|�I�ł������Ǝv���̂ł���B
����ȂƂ��납����e�����Ă܂����A�����͊������Ȃ��l�ɂ��Ă��ł�����ǂ��A����������D���ł��B����ɓ��|�Ƃ̕��������������Ȃǂ�����֖�̕������܂����B����ɍ�i�Ɏg���Ă���͓̂��{�̓y�ł��B���������ς�u���v�Ƃ����\�����g��������������Ȃ����Ǝv���Ă��܂��B
����
�Ȃ��A�u���v�Ƃ����f�ނ������̂ł��傤���B
�[��
�����Ƃ����̂͑傫��������ƃJ�[�r���O�ƃ��f�����O�̍�ƁA�܂蒤���ƒ��Y�̎d���Ƃ�����ɕ����邱�Ƃ��ł��܂��B
�J�[�r���O�Ƃ����͍̂��ގd���ł��B�ł܂肩�璆�ɂ���J�^�`��o���Ă����A���ꂪ�����A���ނ��Ă������ƂȂ�ł��ˁB
�ŁA���f�����O�Ƃ����͓̂y�Ő����Ă�����Ƃ̂��ƂȂ�ł��B�Ȃ��Ƃ���ɑ��݂����Ă������Ă����B�܂�Ő����̐����ł��B
�l�́A��̂Ȃ�����J�^�`���������Ɓi�܂�J�[�r���O�j�����܂蓾�ӂł͂Ȃ������̂ŁA���f�����O�Ő��삵�Ă������ƂɌ��߁A�ŏ��͓S�ƏĂ�����g�ݍ��킹����i�������Ă��܂����B
�S����ɂȂ������i�����������肷��̂ŁA���ƍ�ƓI�ɂ̓��f�����O�I�ł������A������ƈႤ�ȂƎv���A���̕��������Ő��삷��l�ɂȂ�܂����B
���f�����O����N�����f�ނɂ́A�v���X�`�b�N��u�����Y�Ȃǂ����Ȃ��̂�����܂����A����炪�����I�ȕ\���̍ŏI�n�_�ɓ��B����܂łɁA�قƂ�ǂ̏ꍇ�͏��Ȃ��Ƃ�1��͌^�ɂ�������Ƃ��K�v�ɂȂ��Ă��܂��B����͂��������p�ł���ł�����ǂ��A�l�̒��ł��̍�Ƃɑ��Č������̂悤�Ȃ��̂���������ł��B1��Ⴄ�^�ɒʂ��āA����1�m���ł��Ă�����X�ɂ������Ă����B���̊ԂɂȂɂ���߂Ă��܂��Ƃ������B�ŏ��ɂ������Ƃ��̃��A���e�B�݂����Ȃ��̂��A���S�ɂ������������Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂��̂ł��B
����ŁA���f�����O�������̂����̂܂܃J�^�`�ɂł����@�͂Ȃ����ƍl�����Ƃ��A���܂��ܑ�w�̎��̃T�[�N�����Ă����̃T�[�N�����������Ƃ�����A���Ƃ���Ȃ�u��������A���Ƃ����f�ނ��g���A���f�����O�̂܂܂��������ɂł����Ȃ����v�ƁB

�h���[�C���O�@�C���N�E�A�N�����E���@h39×��27�p�@2010�@�@�V�h��ȉ�L |
����
�u�͂��߂ɂ��������������̂܂܂���i�ɂł���v�A�ȑO�����悤�ɓ���������Ƃ��痘�_�Ƃ��ĕ��������Ƃ�����܂��B
�[�䂳��͂ǂ̂悤�Ȑ�����@�Ȃ̂ł��傤���B
�[��
�܂��̓h���[�C���O���A�F���g�킸�C���N���y�������M�̃��m�N�������ōs���܂��B1�̍�i�ɑ��ăX�P�b�`�u�b�N1���Ƃ������Ƃ��A�����ȂƎv����܂ł����ƕ`���B����͂قƂ�Ǎ�i�Ƃ��Č����邱�Ƃ͂Ȃ��āA�����̂��߂́A�����̐���̂��߂̃A�C�f�A�ł�������܂���B
����ŁA���ʂ̒��łȂ�ƂȂ��C���[�W���������Ă����痧�̂ɋN�����܂��B
�Ⴆ����̗l�ɗ��\���锖����i�́A�^�ɂȂ镔�����e���v���[�g�ł����āA����ɉ����ĕ\��������A�e���v���[�g�ɂ��ė���������B�^��������������ӂ��͐�ɍ����܂���ˁB
���ꂼ��͂܂����C�̉�ł����Đؒf���A���ꂩ�痠������o���܂��B���C�̂܂܂ł͌��݂Ƀo���c�L�������Ċ���Ă��܂��̂ł��B����ŏĂ�������Ă����p�̃p�e�Ȃǂł������ďC�����܂��B�Ƃ����킯�Ŕ����Ă����g�͋Ȃ�ł���B
���m�ɂ���Ă͓��|�̒ق�����悤�ȗς݂̎�@�ł������肷���ł����ǁA�S�y�͏d�͂Ɏア�f�ނȂ̂ŁA�d�͂��ז������ėς݂��Ƃ���h���J�^�`���łĂ��܂��B�����������ꍇ�́A���C�̉��肾�����������ł��B
���̂��ƍŏI�I�Ȓi�K�ɂȂ��āA�������ŏ��ɕ`�����h���[�C���O����C���[�W��c��܂��āA��i�Ƃ��Ẵh���[�C���O��`���܂��B

�smountain / hand�t�@ ���@h10×w21×d10�p�@2010�@�@�V�h��ȉ�L |

�smountain / hand�t�@ ���@h12×w24×d12�p�@2010�@�@�V�h��ȉ�L�@ |
����
�ǂ�����Ƃ��������ڂɂ��ẮA���͌y����i������Ƃ������Ƃł��ˁB
���̃u�����Y��S�̂悤�ȍ����ۂ��F�ɂ́A�������R�͂���̂ł��傤���H
�[��
������ł܂������A�l�͂��Ƃ��ƓS�ō�i�����肽��������ł��B
�S���ĔނƂ��ۖ_�Ƃ��A�����������ނ��A�@������A�Ȃ����肵��3D���`�Â����Ă�����ł����A����͌��\�ȘJ���ŁA���Ԃ�������܂��B���Ԃ������邱�Ƃ������Ƃ����Ă����b�ł͂Ȃ��āA�C���[�W��̍ŏI�I�ȃJ�^�`�ɂł��邾�������X�g���[�g�ɓ��B�������āA����S�y�̊����������Ȃ��čŌ�ɂ͓S����߂邱�Ƃɂ�����ł��ˁB
�ł��S�̎������Ă����̂�����ς�D���ŁB���̋C�������c���Ă��邩��A���������F��I��ł��܂��̂�������܂���B�����֖�́A�l���l���Ă������֖�ŁA����10���N�ȏ�g���Ă��܂��B
�����ЂƂ��R�������āA�͂�����Ɨ��̂̏�ɐF���������F���ڂ��Ă��܂��ƁA�l�̏ꍇ�������肱�Ȃ��Ȃ��Ă��܂��Ƃ����̂�����܂��ˁB�\���ɂ���Ă͌��ʓI���Ǝv����ł����A�Ȃ��Ȃ���肭�����Ȃ��B�R�������Ȃ��ł��B
����
���x�̍�i�A�smountain / hand�t�̃V���[�Y�͂�����ƐF�݂��������܂��ˁB
�[��
�����ł��ˁB���N���N��2�N�Ԃɂ킽���āA4����1�_���i��������Ă����V���[�Y�����܂��āA�N��60�_���炢����܂����B���̂Ƃ��ɂ��낢������I�Ȃ��Ƃ�������̂ł����A���̒��Ŗʔ����Ȃ肻���ȗv�f��������������Ă��ꂩ�炢�������ȂƎv���Ă��܂��B
����̂��̂͂����傫�ȍ�i�ɂ��ǂ��đ��e�A�Ƃ��������ł��ˁB���i�ƌ����Ă�50cm�l�����炢�̃T�C�Y�ł����B
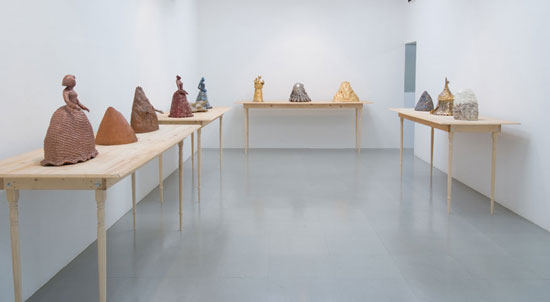
��L����̔����@�V����̎��_2009�@�W�����i�@�@�M�������[�Ȃ� |

�i���j�sthe tower is burning�t�@ ���@h48×w20×d20cm�@
�i�����j�sman / beard�t �@ ���@h37×w41×d26cm�@
�i�E�j�smountain / hand�t �@ ���@h38×w50×d19cm�@2009�@�@
�M�������[�Ȃ�
|
����
���̐F�͏ォ��h���Ă���̂ł��傤���H
�[��
�����A���̐F�͓h���Ă���킯�ł͂���܂���B
�Ă��Ɣ��F����痿����荞�y���g���Ă��܂��B�����������͂��ɐςݏグ�Ă����āA�ォ�獕���u�D���i�ł����傤�j�v�������܂��B���ꂪ���������ƂɁA�N�������ł��X�N���b�`���O�悤�ɁA����Ē����Ă����B�ŏĂ��ƁA����ꂽ�����������̐F�����F����Ƃ����킯�ł��B
����
�ł͂��̑傫�ȎR�̍�i�́A�D���傤����菜���ƂƂĂ��J���t���ȗ��̂ɂȂ�̂ł��傤���B
�[��
�����ł��ˁA�ł��S������Ȃ��ł��B�啔���͂����Ɠ����y���g���Ă��܂��B�F�������y�͔��F��D�悵�Ă���̂ŁA�傫���ɑς����Ȃ��ア�y�Ȃ̂őS������ł����Ă����̂͂Ȃ��Ȃ�����ł��ˁB
�܂��A�����̒��ŁA�֖��D����������Ƃ������Ƃ́u�I�u���[�g�ɕ�ށv�Ƃ����悤�Ȋ��o������܂��B���̂܂܂��Ɩl�̎w�̂��Ƃ��̂��Ƃ������ƍr�X�����c���Ă����ł��B�����1�w�̂��邱�ƂŐ��X�������銴���𒆘a���Ă���Ƃ������B
�ł�����͂���������Ƃ҂�����Ƃ���g�����������Ȃ����A�܂��܂��l���Ă����Ȃ��Ă͂����Ȃ��ȂƎv���Ă��܂��B

�smountain / hand�t�@ ���@h70×w180×d20�p�@2010�@�@�V�h��ȉ�L |