
痕跡−戦後美術における身体と思考
TRACES - Body and Idea in Contemporary Art
東京国立近代美術館
2005年1月12日(水)―2月27日(日) |
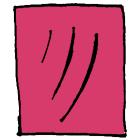
フォンタナ「空間概念」1962 |
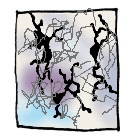
嶋本昭三「作品」1954 |
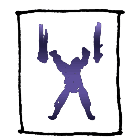
クライン
「人体測定(ANT170)」1960 |
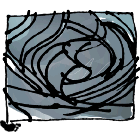
白髪一雄「天魁星呼保義」1964 |
 |

「幻想の彼方へ」(渋澤龍彦著 河出書房新社 1999年5月10日第7版) |
 |
|
|

|
今年1月に東京国立近代美術館(東京・竹橋)で痕跡展が開催された。この美術展は、20世紀後半の分かりにくい美術作品を独特の見地(記号論)から分析するもので、難解な部分があるものの、分かりにくい美術作品理解に大いに役立つ美術展であった。以下が私の同展から得た感想である。
同展図録の冒頭で、例えば、カンヴァンスに切込みを入れる(フォンタナ)とか、穴を開ける(嶋本昭三)などの作品について、多くの人たちは美術作品として承服しがたいものがあるとみるであろう、しかしこれらの行為は、決して彼らがスキャンダルを起こそうとして実行したものでなく、やむにやまれぬ衝動が彼らをしてカンヴァスの毀損へと向かわせたのである。と説明している。
さらに、絵画を見る場合、人は一般に、そこに何が描いてあるか、描かれた内容を見ようとする。人物画とか風景画とかは特にそうである。しかし、ここでの見方は全く異なる。作家の持つ、やむにやまれぬ衝動の結果を痕跡として見るというのである。
例えば、フェルメールの“デルフトの眺望”を見る場合、普通は当時のオランダの街景をそのまま再現したものだと見るが、痕跡として見る場合、フェルメールの筆さばきにより、光の効果としての街の陰影がみごとに表現されていると見ることができる。としている。
前者は一般的な見方だが、後者はフェルメールの描く1本1本の線、あるいは筆触を痕跡としてみるということであろう。
作品をみる場合、常に前者、後者、両方の見方があり、前者は、描く対象と作品(結果)との間に相似関係が、後者は、作家の衝動(原因)と痕跡(結果)との間に因果関係があるとみるのである。
後者の視点に立つと「抽象、具象の別」、「平面、立体の別」、「美しい、そうでないの別」、「分かり易い、分かり難いの別」などはまったく関係なく、この痕跡にいたるプロセスを含めて作品を見るべきだといえるのではないか。
以上の見方は、極度に概念化された20世紀後半の美術を一種の袋小路から解放する手段として重要な役割を担った。と記しているが、まさにその通りであろう。
態様により痕跡を次のように分類している。“表面”、“行為”、“身体”、“物質”、“破壊”、“転写”、“時間”、“思考”である。
必ずしも同分類の作品が同じ考え方に基づいているわけではないが、分類された作品を見ると、美術史上では全く繋がらなかった作品同士が、同じ痕跡としての土壌上で繋がるのである(詳細は図録参照)。
例えば、フォンタナの「空間概念」、嶋本昭三の「作品」、李禹煥の「刻みより」、「つきより」などは「表面」という土壌上で繋がり、「身体」という土壌では、イヴ・クラインの「人体測定」、ジャスパー・ジョーンズの「ハトラス」、白髪一雄の「天魁星呼保義」などが繋がる。
以上により、作品の見方がガラリ変わり、時代の傾向、考え方の傾向などを含めて作品理解をより広く、深くすることができるであろう。
ほぼ同時代の作品を同種の痕跡として見るという意味で、これらは“横の関係”があるということができるのではないか。これは時代背景を見るのに役立つといえる。
また、この視点に立つと、過去の美術史上でも同種に属すと考えられる作品の先例をみることができる(図録参照)。興味のあるところであり、ここでも作品が繋がる。
例えば、
- クラインが操作するのが「女性という生きた絵筆」であり、この意味でクラインの「人体測定」は西欧における裸体画の正嫡だ。
- メンディエッタやニッチの血まみれのパフォーマンスはあまりにも極端な作品だが、西欧美術史を振り返ると血に彩られた暴力の表現は決して異例ではない。
- ラウシェンバーグの作品(自動車タイヤプリント)は自動車のタイヤの痕跡を紙に転写する一種の版画として成立している。
- ジャスパー・ジョーンズの「電球」、ロバート・モリスの作品「ラビング・ドローイング」を指して、このような表現の先例はシュルレアリストのフロッタージュに求められる。
などとしているが、これらを“縦の関係”があるということができるのではないか。
“横の関係”だけでなく、“縦の関係”から見ても美術史を離れて新たな発見が出現してくる。これまで単線的に美術史に沿って作品を理解していたが、それとは別にこの美術展後、より広い見方で作品に接することができ、作品理解の幅が広がったと言える。
たまたま渋澤龍彦の著書「幻想の彼方へ」(河出文庫)を見ていた。これに関連すると思われる興味ある部分に出会った。少し長いが、ここに紹介したい。
「セザンヌ以後の近代絵画の主流に属する画家たちは、ピカソから抽象表現主義の戦後派作家にいたるまで、すべて新しい絵画空間の創造に努力を集中し、造形的関心をなによりも優先させてきたが、ただシュルレアリストだけは、そのなかにあって例外的な立場を守っていた、と私は考える。・・・シュルレアリストたちは、新しい絵画空間の創造にはなんら寄与せず、ただ既知の絵画空間的世界の現象や物体の序列を狂わせるということ、すなわち・・・『デペイズマン』の理念のみを忠実に守ったのである。進歩的歴史観に対応する近代絵画の正統的な空間意識の探求を拒否し、造形至上主義的な一切のメチエをみずから放棄して、彼らは古くてしかも新しい、自然の永遠のヴィジョンがあたえる情緒的効果をもっぱら大事にしたのであった。芸術上の古さと新しさとの区別を認めていなかったからこそ、ブルトンのいわゆる『ウッチェロはシュルレアリストである』とか『アルチンボルドはシュルレアリストである』とかいった、年代記的な歴史観をしりぞけた、独特の美術史の再編成がシュルレアリスムにおいて初めて可能となったのだ。言葉を換えれば、このことは、思想によって美術の歴史を再編するということにほかならず、シュルレアリスムはたしかに、ひとつの思想運動だったのであり、シュルレアリスム以外の20世紀のどの流派にも、このような全体的な人間回復の志向は読みとれないのである。・・・」(同書149〜150ページ)
渋澤龍彦の「思想によって美術の歴史を再編する」と「痕跡展の視点」(縦の関係、横の関係)とは、美術作品を多角的に理解するための有効な見方であると思えてならなかった。
美術の世界も一般のわれわれには理解が非常にできにくくなってきているが、その突破口としてこのような考え方も面白いと思うのである。
著者プロフィールや、近況など。
菅原義之
1934年生まれ、中央大学法学部卒業。生命保険会社勤務、退職直前の2000年4月から埼玉県立近代美術館にてボランティア活動としてサポーター(常設展示室作品ガイド)を行う。
・アートに入った理由
1976年自宅新築後、友人からお前の家にはリトグラフが似合うといわれて購入。これが契機で美術作品を多く見るようになる。その後現代美術にも関心を持つようになった。
・好きな作家5人ほど
作品が好きというより、私にとって興味のある作家。クールベ、マネ、セザンヌ、ピカソ、デュシャン、ポロック、ウォーホルなど。 |

|
 |
|