

痕跡−戦後美術における身体と思考
TRACES - Body and Idea in Contemporary Art
東京国立近代美術館
2005年1月12日(水)―2月27日(日) |

フルクサス展−芸術から日常へ
うらわ美術館
2004年11月20日(土)〜2005年2月20日(日) |

マルセル・デュシャンと20世紀美術展
――芸術が裸になった、その後で
横浜美術館
2005年1月5日(水)〜3月21日(月・祝) |

愛と孤独、そして笑い
東京都現代美術館
2005年1月15日(土)〜3月21日(月) |

21世紀の出会い―共鳴、ここ・から
金沢21世紀美術館
2004年10月9日(土)〜2005年3月21日(月・休日) |
|
|
21世紀への推移を見る
TEXT 菅原義之
|
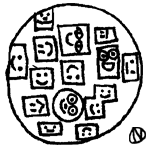 |
幸いなことに今年は、年頭から関心のある美術展にめぐり合った。「痕跡−戦後美術における身体と思考」(東京国立近代美術館)、「フルクサス展−芸術から日常へ
」(うらわ美術館)、「マルセル・デュシャンと20世紀美術展」(横浜美術館)、「愛と孤独、そして笑い」(東京都現代美術館)、「21世紀の出会い―共鳴、ここ・から」(金沢21世紀美術館)である。いずれも興味をもって見た。
これらの美術展を総合してみると、20世紀から21世紀美術への推移が感じられた。
「痕跡展」は、20世紀後半に焦点を絞り、分かりにくい時代の美術作品を“美術の流れ”とは別な切り口で分類し展示する方法。新たな発見があり作品理解に役立った。
また、「フルクサス展」では、コンセプチュアル・アートやパフォーマンスに大きな影響を与えたフルクサス作品を多く見ることができた。
その後「デュシャン展」を見た。分かりにくいデュシャンの作品に少しでも興味をもたせようとする美術館側の工夫のあとが見られた。デュシャンの作品とその後の作家の類似作品とを比較展示し、興味の度合いを所定用紙に投票させるもので、ややわずらわしいもののデュシャン理解にはよい試みであった。全体にデュシャンの影響の大きさを改めて感じた。
以上は20世紀、特に20世紀後半を対象とする作品展であった。興味はあったものの全体に“重い”、“分かりにくい”、“疲れる”、“やや暗い”感じの作品が配された美術展だったと言っていいであろう。
一方、都現美開催の「愛と孤独、そして笑い展」の中には“面白い”、“胸を打つ”、“分かりやすい”作品があった。たとえば、澤田知子の「School
days」などは気がついた瞬間笑った。発想が面白かった。また、出光真子の作品は分かりにくいビデオ作品でありながら誰にでも容易に理解させる工夫があり、心に訴えるものがあった。
21世紀的感覚が込められた美術展だったと言えるのではないか。
その後、金沢の21世紀美術館に行った。“現代美術展は人気がない”が通例であるが、ここは違った。開館2ヶ月で、年間入館予定者の30万人をクリアしたという。
なぜか。
一つはグランド・オープニング展であり、珍しさがあったり、金沢市内の小中学生全員を参加させる遠大な企画があったりで多くの人たちが訪問したと推測できる。しかし、主な理由は、参加作家の質が高く、展示作品の内容が全般に見てよかったからであろう。そこには前述した20世紀の作品群とは違ったタイプが多く展示されていたように思う。美術館側でも意識的に作家選択をしたであろうが「参加型・体験型の作品」、「視覚に心地よく訴える作品」が多かった。
前者では、カールステン・へラーの「自動ドアー」、レアンドロ・エルリッヒの「スイミング・プール」、ジェームズ・タレルの「ブルー・プラネット・スカイ」、後者では、ゲルダ・シュタイナー&ユルグ・レンツリンガーの「ブレインフォレスト」、サラ・ジーの「アート・オブ・ルージング」、マイケル・リンの「市民ギャラリー」などが強く印象に残った(後期展示から)。
作家の年齢を見ると多くが1960年代生まれ、次は70年代生まれだった。この年代といえば、前述の難しいコンセプチュアル・アートの盛んな時代に生まれたか、その前後の人たちである。成長するに及んで、コンセプチュアル・アートに触れて、参考にしつつも美術のあるべき姿を見直したか、反面教師として自分たちのアートを思考したのではないかと思えてならなかった。
アメリカのクリス・バーデンの「メトロポリス」も人目を引いた。彼は1946年生まれでほかの作家と比較して年長である。1971年に身体的表現(ボディ・アート)として自分の左腕をライフル銃で友人に撃たせ、名を知らしめたが、コンセプチュアル・アートの代表作家の一人であった。
このたびは「メトロポリス」と題して、大都市のエッセンスを巨大な立体作品で表現し、以前と異なるタイプの作品制作に至っている。
クリス・バーデンを含めて若い作家たちは、いわゆるコンセプチュアル・アートを越えて21世紀型作品を制作していると言えるのではないか。
20世紀後半の“重い”、“分かりにくい”、“疲れる”作品に対して、全体に“洗練されている=あかぬけしている”、“心地よい”、“面白い”、“明るい”、“身近に感ずる=庶民的”作品が多く、これこそ21世紀型の美術だと思うがどうであろうか。
20世紀に入り、キュビスムを始め、抽象絵画、ダダ・シュルレアリスムが出現した。後半のコンセプチュアル・アート時代には美術が根源を極めるところまで行き、一般の人を寄せ付けなくなったが、21世紀に至り時代の変わり行く様を的確に捉え、結果として多くの人たちに興味をそそる美術展を出現させたのではないか。
キュビスム時代からほぼ100年を経て、ようやく長いトンネルを抜け出たかのようでもあった。そしてこの金沢21世紀美術館のグランド・オープニング展が、時代を変えるきっかけになればと思うこと頻りであった。これからが試練のときであろう。今後の発展を期したいものである。
著者プロフィールや、近況など。
菅原義之
1934年生まれ、中央大学法学部卒業。生命保険会社勤務、退職直前の2000年4月から埼玉県立近代美術館にてボランティア活動としてサポーター(常設展示室作品ガイド)を行う。
・アートに入った理由
1976年自宅新築後、友人からお前の家にはリトグラフが似合うといわれて購入。これが契機で美術作品を多く見るようになる。その後現代美術にも関心を持つようになった。
・好きな作家5人ほど
作品が好きというより、私にとって興味のある作家。クールベ、マネ、セザンヌ、ピカソ、デュシャン、ポロック、ウォーホルなど。 |

|
|